税理士による書面添付制度を活用して税務調査対策を最適化する方法
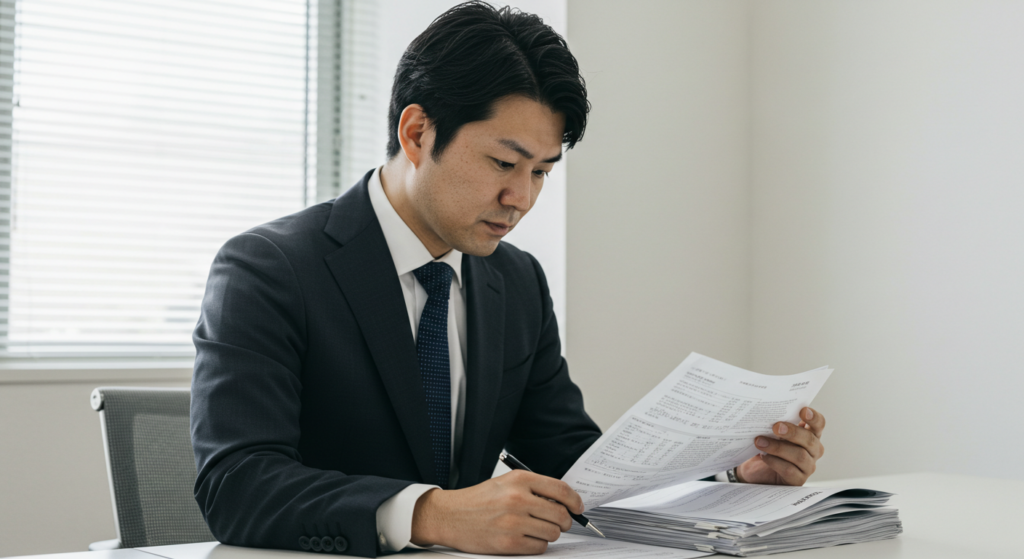
皆さんこんにちは。クラウド会計で経営支援を提供する千葉の税理士、中川祐輔です。
毎週月曜日に、経営者なら知っておきたい「税務調査」についての知識を解説しています。
中小企業の経営者の皆様にとって、「税務調査」という言葉を耳にするだけで、何かと落ち着かない気持ちになることは少なくありません。
実際に調査が入った場合、どのような書類を求められるのか、どこまでの説明が必要なのかなど、不安に思う点が多いからです。
こうした不安を軽減し、万が一の税務調査に備えるための有効な手段として、当事務所で活用しているのが「書面添付制度」です。
本記事では、この書面添付制度の基本的な仕組みや期待できるメリット、そして経営者として押さえておくべきポイントを分かりやすくまとめました。
税務調査への不安と書面添付制度の概要
1. 多くの経営者が感じる税務調査のプレッシャー
税務調査とは、税務署が申告内容の正確性を検証するために行う手続きです。
経営者や経理担当者が調査官から質問を受けたり、売上や経費を証明する資料を提示したりする場面を想像すると、心配になる方が多いでしょう。
特に、初めて調査を経験する場合や、日頃から経理処理に不安がある場合はなおさらです。
しかし、税務調査=違反や不正を疑われているというわけではありません。
法律や規定上、定期的に行われる可能性があるため、いずれ訪れるかもしれない「もしも」に備えておくことが大切です。
2. 書面添付制度とは
書面添付制度は、税理士法第33条の2に基づき、税理士が確定申告書と同時に、申告内容を確認した旨を記載する書面を添付することができる制度です。
具体的には、次のような特徴があります。
- 申告書への信頼性を高める
税理士の専門家としての立場から、「この申告内容は帳簿などを基に確認しています」という意思表示になります。 - 後付けは不可
確定申告書の提出時に一緒に添付しなければなりません。後から書面だけを送付することは認められていません。 - 実地調査が省略されるケースが多い
書面添付制度を活用することで、税務署は「既に税理士が内容を精査している」と考え、実地調査へ進む必要がないと判断する可能性が高くなります。
このように、書面添付制度は税務調査のリスクを低減し、経営者の不安を軽減するための有力な方法として広く注目されています。
書面添付制度がもたらすメリット
書面添付制度を利用することで得られるメリットは、大きく分けて以下の三つです。
1. 実地調査が省略される可能性が高まる
2014年の「東京税理士界」による税務調査アンケートでは、法人税の申告において
書面添付制度を活用したケースの65.1%で、実地調査(税務署が直接事業所を訪問する調査)が省略されています。
つまり、3件中2件は現地に調査官を呼ばずに済んでいるということです。
これは、税務署側が「既に税理士の専門的なチェックが入っている」と認識することで、リスクが低いと判断しやすくなるためだと言われています。
実地調査が行われなければ、担当者の対応時間や精神的な負担を大きく削減できるでしょう。
2. 税務調査への対応コストが軽減される
もし実地調査になったとしても、事前に税理士が細かいチェックを行い、申告内容を整理しているため、調査期間の短縮や指摘事項の減少が期待できます。
結果として、経営者や経理担当者が税務調査にかける時間や労力が抑えられるメリットがあります。
限られた経営資源を、本業の成長や重要な意思決定に振り向けられるという点は見逃せません。
3. 経営管理体制の強化につながる
書面添付制度を活用するにあたっては、税理士と企業が普段以上に緊密なコミュニケーションをとり、記帳内容や経営状況を確認・共有する必要があります。
これを機に、会計データの正確性や内部管理体制を見直せば、経営状況をより正確に把握できるようになり、将来的な経営戦略の策定にもプラスに働きます。
書面添付制度を活用した税務調査の流れ
ここでは、実際に書面添付制度を利用した場合のおおまかな流れをご紹介します。
税理士とのやりとりが中心となりますが、経営者として大まかなプロセスを把握しておくことで、よりスムーズに準備できるでしょう。
- 申告書への書面添付
税理士が作成した確定申告書に、書面添付を行ったうえで税務署へ提出します。後から追加提出することはできないため、日頃から正確な記帳や経理処理を行っておくことが大切です。 - 税務署による書面の確認
書面添付がある場合、税務署は「税理士が事前に確認している点」を踏まえたうえで、申告内容を審査します。この段階で明らかな誤りや疑問点がなければ、実地調査が省略される可能性が高まります。 - 調査省略または実地調査への移行
書面添付によって疑義が解消され、経理処理や申告内容に問題がないと判断されれば、そのまま調査を行わずに完了することがあります。一方で、どうしても確認したい点が残る場合には、実地調査へ進むケースもあります。
なお、書面添付の対象外になっている項目や、特殊な取引などがある場合は、税務署が追加で確認を求めることがあります。
そうした場合でも、あらかじめ税理士とコミュニケーションを密にしておけば、迅速に対応可能です。
経営者として押さえるべきポイント
書面添付制度を利用して税務調査リスクを最小限に抑えるためには、経営者自身が日頃から準備を整えておくことが重要です。
以下のポイントを意識して、円滑な手続きを目指しましょう。
1. 正確な記帳と資料の保管
どんなに優秀な税理士でも、もとになる帳簿や証憑が不十分であれば、正確な申告書の作成は難しくなります。
領収書や請求書などの証憑を適切に管理し、会計ソフトへの入力も随時行うなど、正確な記帳を意識しましょう。
2. 税理士との密なコミュニケーション
書面添付制度を活用するには、税理士と企業側の連携が欠かせません。
疑問点や不明点があれば早めに相談し、経営状況の変化や特殊な取引が発生した場合は、速やかに共有することが大切です。
お互いに最新の情報を把握していれば、書面添付書類の作成もスムーズに進みます。
3. 経営状態の定期的な見直し
税務調査対策というと、どうしても「調査をいかに回避するか」に目が行きがちですが、それだけではありません。
会計データの正確性や経理処理の透明性を高めることで、自社の経営状態を客観的に分析しやすくなるという利点があります。
定期的に自社の財務諸表を見直すことで、今後の経営戦略や資金繰り対策にも役立つため、一石二鳥の効果が期待できるでしょう。
まとめ
税務調査は「いつ実施されるか分からない」ため、経営者の方にとって常に漠然とした不安の種になりがちです。
しかし、書面添付制度を活用すれば、実地調査を回避できる可能性が格段に高まるだけでなく、調査があったとしても事前準備が整っている分、負担を大幅に軽減することができます。
実際、書面添付制度を利用したケースでは65.1%という高い割合で実地調査が省略されているという統計データも示されており、多くの中小企業がメリットを享受してきました。
「もし税務調査が来たらどうしよう」と不安を抱える前に、まずは税理士と一緒に書面添付制度の利用を検討してみてください。
しっかりとした経理処理と正確な申告書の提出ができれば、税務署からの信頼度も高まり、経営者の皆様が本業に専念できる環境づくりに役立ちます。
上記の内容が、税務調査に対する備えとして「書面添付制度」をご検討される際の参考になれば幸いです。
税理士との二人三脚で、適切な会計処理と書面添付を行い、安心して事業運営に邁進できる体制を整えていきましょう。

