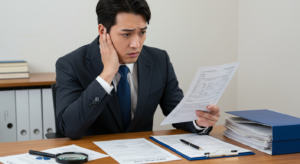売上を安定させる「構造的リピート」戦略 – ギフト化の活用法

皆さんこんにちは。クラウド会計で経営支援を提供する千葉の税理士、中川祐輔です。
毎週火曜日に、経営者なら知っておきたい「売上増加」についての知識を解説しています。
多くの中小企業では、どのようにすればお客様に継続的に来店してもらえるのか?という大きな課題を抱えています。
一度ご利用いただいて終わりではなく、何度も足を運んでもらい、安定した売上を確保するための仕組みづくりは、ビジネスを継続・拡大していくうえで重要な要素です。
本記事では、その課題を解決するための「構造的リピート」という考え方に注目し、その中でも特に効果が高く、導入もしやすい「ギフト化」について詳しくご紹介します。
ギフト化を導入すると、お客様に自然と再来店いただける状況を生み出せるだけでなく、コスト面でも比較的低リスクで始められる特徴があります。
売上を安定させたいと考える中小企業にとって、有用なヒントになるはずです。
構造的リピートとは?
まずは「構造的リピート」の概念を整理しましょう。
構造的リピートとは、ビジネスの仕組みそのものを工夫して、意図せずともお客様がリピートせざるを得ない状況をつくり出す戦略のことです。
単に「次回来店時に割引が受けられるクーポンを配布する」ような施策とは異なり、「必ず再来店が必要になる仕組み」を提供し、お客様が自然とお店を選び続ける状態を実現させます。
たとえば以下のような例が、構造的リピートの代表的な形です。
- 定期契約型:学習塾の月謝制やスポーツクラブの月会費など、契約期間中は定期的に利用してもらえる仕組み。
- ギフト化(今回紹介するモデル):自宅用で消費する商品をギフト用にチェンジすることで、お中元やお歳暮、お贈り物、記念日等で利用してもらえて結果リピートが増える仕組み。
このように、割引やポイントカードなどの一時的な促進施策とは異なり、ビジネスモデルの設計段階で「必ずリピートにつながる仕組み」を組み込んでおくのが、構造的リピートの最も大きな特徴です。
「構造的リピート」について詳しく知りたい方は、たった3つのポイントで売上が安定する!「構造的リピート」という考え方で基本的な考え方を解説していますので、ぜひご覧ください。
ギフト化戦略とは?
まず「ギフト化」とは、自分や家族で普段使っている商品(特に日常消耗品など)を、贈り物用に演出やパッケージを工夫し、贈答品として販売展開することを指します。
お中元やお歳暮、誕生日などの記念日や季節の行事など、贈り物が必要になるシーンは多種多様です。
そうした機会に「自分が愛用しているものをあの人にも贈りたい」という感情が生まれれば、自然とリピート購入や追加購入が発生します。
ギフト化に必要な要素
ギフト化を成功させるために、店舗や企業側には以下のような要素が求められます。
- 贈り物としての適切な演出
商品自体だけではなく、包装やメッセージカード、リボンなど、贈り物として受け取ったときに特別感を演出できる仕掛けが必要です。 - 魅力的なパッケージ作り
「パッケージは商品の顔」と言われるほど、視覚的な印象は重要です。パッケージによって、商品の価格帯やブランドイメージが大きく左右されます。 - 送る目的に応じた商品展開
結婚祝いや出産祝い、季節の挨拶用など、贈り先や贈るシーンに合わせたラインナップがあると、顧客は選びやすくなります。
これらの要素を組み合わせることで、普段は自宅用にしか買わない商品でも「贈答品として買い足す」という行動を引き出せるようになります。
お米専門店の具体的事例
ギフト化戦略によって成功を収めている事例として、お米の専門店が挙げられます。
通常、お米は日常的に使われる食材であり、以下のような特徴から「定期的に購入するけれど、あまり切り替えをしない」という購買行動をとりがちです。
- 銘柄か量でしか選択肢がない
お米は有名な銘柄や価格、内容量で比較されることが多く、差別化が難しい場合が多いです。 - スイッチングコストが高い
一度おいしいと思った銘柄を選ぶと、別の銘柄に乗り換えるのに抵抗を感じる人も少なくありません。安心感や慣れが重視される傾向があります。 - 価格競争に陥りやすい
スーパーやネット通販では「より安いところで買いたい」という動機が強く働き、価格が決め手になる場合が多いのです。
ところが、あるお米専門店は「ギフト化」という観点で新たな市場を創り上げて成功しました。
具体的には、以下のような工夫を行っています。
- 12色のお米という独自コンセプト
お米マイスターが厳選したさまざまな品種を取りそろえ、「料理に合わせて楽しめるお米」という打ち出し方をしています。
さらに、少量パッケージを採用することで気軽に複数種を試せる仕組みを構築し、消費者に“選ぶ楽しさ”を提案しています。 - 用途別の展開
出産祝いでは赤ちゃんの体重に合わせたお米を贈るなど、実に多彩なギフト企画を立ち上げています。
たとえば、下記のような用途別の展開により、「これはあの人にピッタリだ」と思ってもらえる機会が増えます。- 季節のご挨拶用(お中元・お歳暮)
- 出産祝い:赤ちゃんの体重に合わせたオリジナルギフト
- 結婚祝い
- 新築祝い
- 各種記念日
- 贈り物としての付加価値
贈答用としての付加価値サービスも充実しています。- オリジナルメッセージカードを同封できる
- 名入れ対応が可能
- 写真や手紙の同封サービス
これらのサービスを総合的に組み合わせることで、お米という日常的な消費財が「記念日に贈られる特別なギフト」へと姿を変え、価格競争ではない新たな市場を開拓しているのです。
ギフト化戦略が効果的な理由
ギフト化がリピートにつながる要因は、大きく分けて以下の二つが挙げられます。
- 既存商品の価値向上
普段は普通の「自宅用消耗品」だったとしても、パッケージや演出次第で“スペシャル感”を出せます。
特別仕様に仕立てることで、通常より高めの価格帯で販売しても納得してもらえるケースも多く、利益率アップにもつながります。 - 新規顧客層の開拓
ギフトとして受け取った人が、新たにその商品を気に入ってリピート購入してくれる可能性があります。
さらに「贈る」という行為自体が宣伝効果を生み、贈り主と受け取り主の双方に働きかけるため、結果として顧客層の拡大につながります。
単に「おいしいお米を食べたらリピートしたくなる」だけでなく、「今度は私も誰かに贈りたい」という二段階の繰り返し需要が生まれる点が大きなメリットです。
ギフト化導入のポイント
ギフト化戦略を導入するにあたっては、以下の点を押さえておくとスムーズに進められます。
1. 商品選定
まずは「普段使いの商品」または「自宅消耗品」と言えるもののなかでも、ギフトとしての演出がしやすい商品を選ぶことが大切です。
特に高級感があり、普段は自分では買わないような少し贅沢なアイテムが適しています。
たとえばお米や調味料、スイーツ、ドリンクなど、日常的に使うものでも品質やブランド力を打ち出せるものが最初の候補となるでしょう。
2. イメージ作り
次に重要なのが、ギフトとしての演出・イメージ作りです。
単に包装紙や箱を変えるだけではなく、ストーリーやメッセージを添えるなど、贈られる側が「特別感」を感じられる工夫を凝らしましょう。
具体的には以下のような取り組みが効果的です。
- ブランドストーリーの明確化
商品にまつわる背景や製法のこだわり、開発秘話を紹介し、「ここだけでしか手に入らない特別なお米」「生産者の思いが詰まった調味料」などの物語を伝えます。 - パッケージデザインの統一感
ギフト用パッケージを設計する際、リボンやラッピングの色味、ロゴマークの配置を統一してブランド価値を高めます。
贈る人にとっても「一目で素敵」と思えるデザインが選ばれやすくなるでしょう。
経営判断へのアドバイス
ギフト化戦略を導入する場合、新しい設備投資やパッケージ開発、プロモーションなどに初期費用がかかる可能性があります。
しかし、以下のような状況にある企業にとっては、検討する価値が高いと言えます。
- 新業態への進出を考えている
たとえば、飲食店が物販部門を立ち上げる、食品メーカーが小売専用ブランドを展開するなど、新しいチャネル開拓の際にギフト化を組み込むことで一気に注目度を高められます。 - 新しい設備投資や商品開発を検討している
既存商品のパッケージを変えるだけであれば、比較的スモールスタートで進めることも可能です。
一方で本格的にギフト向けラインを整備する場合は、包装設備や商品ラインナップの拡充が必要になるケースもあるため、事業計画を立てるうえでの検証が欠かせません。
ギフト化はあくまで「普段使いの商品を特別な用途で売り出す」という戦略であり、すべての商品やサービスに適用できるわけではありません。
自社の主力商品がどのようにギフト需要と結びつくのか、顧客はどんなシーンでそれを贈り物にしたいと思うのか、事前の市場調査や顧客ヒアリングが重要です。
まとめ
ギフト化戦略は、通常の自宅用消耗品を「誰かに贈りたい特別な商品」に変えることで、新たな収益源や固定客の獲得につながる可能性を秘めています。
消費者にとっては、日常的に使っている商品だからこそ信頼感があり、「あの人にも体験してほしい」という気持ちが生まれやすいのです。
特にお米専門店の事例に見られるように、工夫次第でギフトの幅は大きく広がります。
少量パッケージと豊富な品種展開を組み合わせれば、消費者が選ぶ喜びを感じるだけでなく、贈られる側も“普段は手にしない特別なお米”を楽しめるため、両者にとって価値を感じやすい仕組みを作れるのです。
またギフト需要そのものは、年間を通じて変動しつつも確実に存在する市場です。
季節の挨拶や結婚・出産などのライフイベント、企業や個人間の祝い事など、多種多様な機会が見込まれます。
本業の売上だけに頼るのではなく、こうしたギフト需要を取り込むことで、リスク分散と収益拡大の両面にメリットをもたらすことが期待できます。
一方で、ギフト化にはパッケージ開発やサービス対応、ブランディングなどの初期投資が必要となるケースもあり、すべての事業に当てはまるわけではありません。
とはいえ、市場調査や商品企画を丁寧に行い、「贈り物として選んでもらいやすい形」を追求することで、会社の在り方や収益構造を大きく変えるきっかけになる可能性があります。
事業拡大を目指す段階で、新しい設備投資などとあわせて検討する余地のある有効な選択肢として、ぜひ「ギフト化戦略」を取り入れてみてはいかがでしょうか。