税務調査の都市伝説を検証!青色申告と税理士関与が与える本当の影響
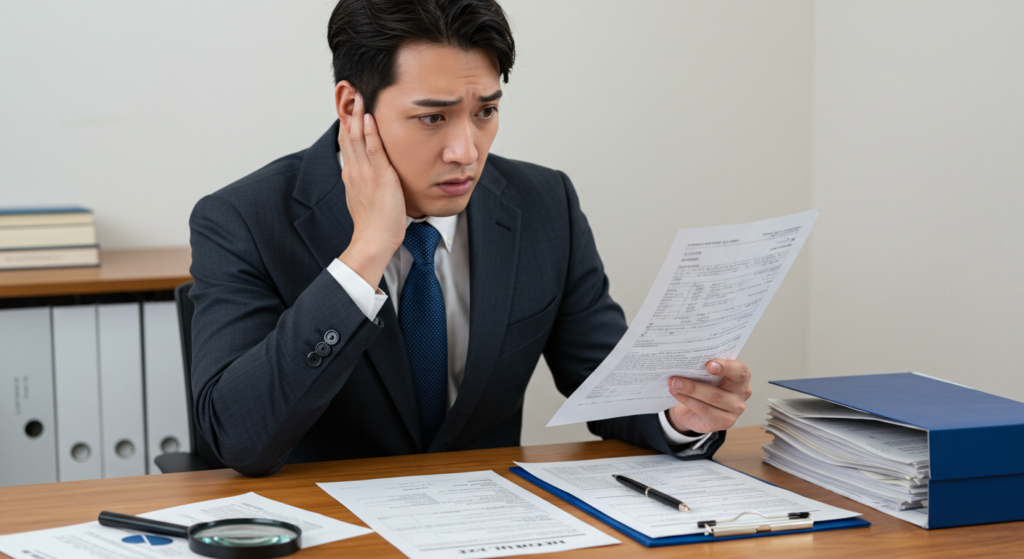
皆さんこんにちは。クラウド会計で経営支援を提供する千葉の税理士、中川祐輔です。
毎週月曜日に、経営者なら知っておきたい「税務調査」についての知識を解説しています。
税務調査というと、多くの中小企業経営者や個人事業主にとって、不安を感じる話題の一つではないでしょうか。
特に「白色申告の方が税務調査に入られにくい」「税理士が関与している方が税務調査に入りやすい」という“都市伝説”がネット上でたびたび議論されています。
しかし、これらの通説は本当に正しいのでしょうか。本記事では、税務調査の実態を多角的に検証してみたいと思います。
はじめに:税務調査をめぐる都市伝説
まず「白色申告だと税務調査の対象になりづらい」「税理士の関与があると逆に狙われる」という話を耳にしたことはありませんか。
こういった噂が生まれる背景には、納税者が青色申告や税理士報酬などのコストを避けたいという心理、もしくは一部で見聞きしたケースを一般化している可能性があります。
しかし、税務調査は決して“噂”や“印象”だけで行われるわけではありません。実際には、国税庁が保有する各種データや調査官の経験則を総合的に踏まえて選定されるのです。
納税者としては、正しい知識を身につけ、自社や自分の事業に合った申告と準備を整えておくことが何より大切になります。
税務調査の基本的な前提を理解する
税務調査について考えるときには、まず国税庁が公表しているデータから、税理士の関与割合や青色申告の割合を確認しておくと、調査に関する傾向が見えてきます。
1. 税理士の関与割合
税理士の関与がどの程度あるかによって、事業規模や経理環境がある程度推測できます。以下の数字を見てみましょう。
- 法人税: 約90%の法人が税理士の関与あり
- 所得税: 約20%の個人事業主が税理士の関与あり
ここで注目したいのは、法人の場合には非常に高い割合で税理士が関わっているのに対し、個人事業主では関与率が低い点です
。税理士が入っているということは、それだけ「帳簿を整備している」「専門家のチェックを受けている」という可能性が高いということでもあります。
2. 青色申告の割合
次に、青色申告の割合を見ておくと、税理士関与との関連性がよりはっきり見えてきます。
- 法人税: 約90%が青色申告
- 所得税(営業等所得の申告納税額がある場合): 約55%が青色申告
法人はほとんどが青色申告であるのに対して、個人事業主は半数強が青色申告を選択しているにとどまります。
これらの数字を見ると、法人の場合は「税理士が関与していれば、ほぼ青色申告」というパターンが多く、逆に言えば「税理士の関与がないと、そもそも事業規模が小さい(=調査の優先度が下がりがち)」とも推測できるわけです。
税務調査の一次選定プロセス
税務調査は、いきなり調査官が訪問を決めるわけではありません。最初に「一次選定」と呼ばれるプロセスが存在します。
ここでは税務署内のシステムによるデジタル選定と、外部からの情報提供が組み合わさっている点が重要です。
1. システム(KSK)によるデジタル選定
国税庁が管理するシステム(KSK)では、納税者が提出した決算書や申告書などの数字を分析・照合し、一定の基準を満たすものをリストアップしていきます。
この段階では、実は青色申告か白色申告か、税理士関与の有無は直接考慮されません。
主に売上・所得状況、経費の伸び率など、数値面から「不自然な動き」があるかどうかがチェックされるイメージです。
2. 資料せんが調査を後押しする
システム選定だけでなく、資料せんの内容も大きく影響します。
資料せんとは、クレジットカード会社や取引先企業などから税務当局に提供される情報で、取引額や支払先など具体的なデータが載っています。
ここから「申告内容と大きく乖離がある」「申告されていない取引がある」といった事実が確認されると、たとえ青色でも白色でも、また税理士関与の有無を問わず、調査対象リストに載る可能性が高まるのです。
法人に対する税務調査の二次選定
一次選定を通過した後、国税局や税務署内の統括官・調査官が最終的な調査先を絞り込む「二次選定」が行われます。
法人の場合、この二次選定で顕著に見られる傾向として、「白色申告または税理士が関与していない法人は後回しになりやすい」という点が挙げられます。
1. 白色申告/税理士関与なしが選定されにくい理由
この背景を理解するには、調査官の「調査効率」を考えなければなりません。
調査官は限られた人数で多くの調査対象を抱えるため、1件あたりにかけられる時間や労力を最適化する必要があります。
具体的には、以下のような理由が挙げられます。
- 調査官には調査件数のノルマがあり、限られた時間で効率的に結果を出す必要がある
- 白色申告では原資資料がまとまっておらず、経理状況も不十分なことが多い
- 税理士が関与していない場合、調査官自身が帳簿や金額を整理する手間が増える
- 結果として、増差(追徴税額)が見込めないケースが多く、優先度が低くなる
上記のように、白色申告や税理士の関与がない法人を調べるのは、調査官側にとって手間ばかりかかって結果(追徴税額)が少ないリスクが高いのです。
そのため、優先度は相対的に下がりやすいというわけですが、だからといって「白色申告ならば絶対調査は来ない」というわけではありません。
大きな申告漏れや資料せんに基づく疑いが浮上すれば、当然ながら調査は実施されます。
2. 選定上の労力とメリット
二次選定では、「同じ労力をかけるなら増差が見込めるところを優先したい」という調査官の現実的な判断が働きます。
結果として、青色申告かつ税理士関与ありの法人は、帳簿がきちんと整っているがゆえに調査が進めやすく、さらに規模も大きい傾向があるため、追徴税額の見込みがあるケースが少なくありません。そのため、白色や税理士なしの法人よりも選ばれやすいのです。
個人に対する税務調査の二次選定
一方、個人事業主の調査選定では少し事情が異なります。
個人事業主の場合、法人ほど青色申告や税理士関与が一般的ではないため、そもそも「白色申告で税理士が関わっていない」状態が多いのです。
1. 個人における白色申告・税理士関与のありなし
個人の所得税申告では、青色申告であっても55%程度にとどまり、残りは白色申告や何らかの理由で簡易な申告方法を選んでいる人が多く存在します。
税理士をつけるほどの売上や利益がない小規模事業主も大勢いるため、調査官からすると「白色申告・税理士なし」の個人事業主はむしろ“普通”という認識になることもあるのです。
2. 調査官の視点
個人事業主を担当する調査官のなかには、「税理士がついていない方が、こちらで細部を確認しやすい」と考える人もいます。
書類が整っていないぶん、不正や申告漏れを見つけやすい場合もあるからです。
したがって、個人の場合は白色申告だからといって調査を逃れやすいとは必ずしも言えないのが現実といえます。
税務調査におけるリスクと専門家の役割
ここで改めて考えておきたいのは、税務調査に対する「備え」の重要性です。
たとえ白色申告で調査確率が下がるかもしれないとしても、いざ調査になった際に適切な対応ができなければ、大きな追徴税額を課されたり、不必要な延滞税やペナルティが発生する可能性があります。
税理士が関与していないケースでは、調査官の質問や指摘に十分に答えられず、事実関係を整理しないまま税務署の主張をそのまま受け入れてしまうというリスクが高まります。
専門家のサポートがないまま調査に臨むのは、言わば防具なしで試合に出るようなものです。
正しい税務調査対策とは
税務調査を「来るかどうか」で考えてしまうと、どうしても「白色申告の方が無難」「税理士に頼むと目を付けられやすい」という短絡的な結論に走りがちです。
しかし、本当に大切なのは「調査に入られた場合、どれだけ適切に対応できるか」という点にあります。
1. 調査確率よりも調査結果に注目する
税務調査は、いわば“いつかは来る可能性がある”ものとして認識しておくことが賢明です。
その際に備えて、日頃から経理処理や帳簿の整理をきちんと行い、疑わしい取引があれば原因を明確にしておくなど、「調査結果」に大きく影響を与える準備をしておくことが大切です。
2. 専門家のサポートでリスク軽減
税理士は、単に申告書を作成してくれるだけでなく、経理処理のアドバイスや節税対策、そして税務調査時の立会いといった多面的なサポートを行ってくれます。
調査の入りやすさばかりを懸念するより、むしろ「税理士がいるからこそ適正な申告と対策ができる」というポジティブな発想を持つことで、長期的に見れば企業活動が安定し、リスクも減らすことが可能となるでしょう。
結論:適正申告と継続的準備が最大の防御策
結論として、「白色申告だから調査されにくい」「税理士がいると調査されやすい」というのは部分的には事例として存在するものの、必ずしも一般的ではないと言えます。
特に個人事業主においては、白色申告が“当たり前”の方も多く、調査対象を決める要因はそれだけではありません。
法人であっても、白色申告や税理士非関与だからといって絶対に選定されないわけではなく、資料せんや不自然な数字が見つかれば容赦なく調査が入り得ます。
もっとも重要なのは、調査が来るか来ないかを気にするよりも、適正な申告や帳簿整備、専門家の活用といった「調査に対する準備」を常日頃から行っておくことです。
青色申告の特典を活かすことや、税理士の専門的なアドバイスを受けられるメリットは、税務調査の有無にかかわらず、健全な事業経営に資する大きな要素となります。
税務調査は一度も受けずに済む人もいれば、何度も受ける人もいます。
しかし、それを「運」で片付けるのではなく、いざ来ても慌てず適切に対応できる体制を整えることこそが、経営者としての最大のリスク対策ではないでしょうか。
納税は事業を継続していくうえで不可欠な責務だからこそ、日頃から正確な記帳と情報管理に努め、“いつか来るかもしれない調査”に備えておきましょう。

