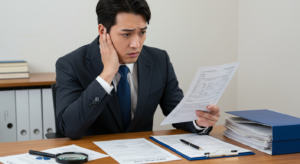銀行格付けの真実:個人の資産力がカギを握る三次評価の実態

皆さんこんにちは。クラウド会計で経営支援を提供する千葉の税理士、中川祐輔です。
毎週金曜日に、経営者なら知っておきたい「銀行融資」についての知識を解説しています。
本記事では、「三次評価」という銀行の格付け評価における最終段階について、その実態と上手な活用方法を解説します。
特に、多くの経営者が抱える「個人資産を銀行に見せること」への抵抗感や誤解を解消し、むしろ企業格付けアップにどのように繋げられるかを具体例とともにご紹介します。
この記事を最後まで読むと、「なぜ経営者個人の資産や返済余力が重要なのか」「三次評価で評価される3つのポイントは何か」「三次評価を味方につけるためにはどのような戦略で情報を開示すればいいのか」などがクリアに理解できるはずです。ぜひご一読いただき、今後の資金調達や格付けアップの戦略にお役立てください。
三次評価とは?―決算書だけでは測れないポイント
銀行は通常、企業の財務状況を一次評価・二次評価で分析します。一次評価は財務指標を中心に、二次評価は事業性などを考慮するのが一般的です。
しかし、三次評価では「経営者個人の資産力」や「経営者自身の返済余力」がさらに詳しくチェックされます。
なぜ銀行がここまで踏み込むのかというと、万が一、会社が十分に返済できない状況に陥った場合でも、経営者自身が返済を支援できる力を持っているかどうかを確かめたいからです。
この「個人資産の裏付け」は、企業の財務指標だけでは把握できないリスクを補完的に評価するうえで欠かせない要素となっています。
とはいえ、多くの経営者の方は「個人の財産まで見せるなんて抵抗がある」「資産をすべて把握されたら根こそぎ担保に取られそう」という不安を抱えていることでしょう。
しかし、実際には「個人資産の開示=すべてを担保に取られる」というわけではなく、むしろ戦略的に開示することが、融資条件の優遇や格付けアップにつながる可能性が高いのです。
三次評価で見られる3つのポイント
三次評価では、主に以下の3つの要素がチェックされます。
ここではそれぞれの要素と、銀行が具体的にどのような視点で評価を下しているのかを詳しく見ていきましょう。
1. 役員報酬と返済余力
まず銀行が注目するのは、経営者の役員報酬が「生活水準と合っているか」「有事の際に返済財源として見込める額はどの程度か」という点です。
あまり知られていないかもしれませんが、役員報酬が高すぎても低すぎても、評価のマイナス要因になり得ます。
- 具体的にチェックされる項目としては、以下のような点があります。
- 役員報酬の金額
- 過去からの推移
- 業界水準との比較
- 会社規模との整合性
- 実際の手取り額
- 所得税・住民税、社会保険料の負担状況
- 実質的な可処分所得
- 経営者の生活水準との対比
- 家族構成、教育費、住宅ローンなどの有無
これらの要素を総合的に見て、最終的に「返済財源としてどの程度期待できるか」を銀行は判断します。
たとえば、年間報酬3,000万円の経営者であれば、手取りは約1,800万円、生活費が約1,300万円と想定した場合、その差額である約500万円が「有事に返済に回せる金額」とみなされます。
役員報酬の設定が実態に即しているかどうかは、銀行からの信頼感にも直結します。
生活費や家族構成を考慮せずに無理やり報酬を上げ下げすると、かえって「何か隠しているのではないか」と疑念を招きかねないので注意が必要です。
2. 経営者個人の資産内容
二つ目のポイントは、経営者個人がどのような資産を保有しているかという点です。
銀行はこれを「追加担保を取りたいから」ではなく、あくまで「返済能力の裏付け」として評価します。
- 具体的に評価される資産には、以下のようなものがあります。
- 不動産資産(居住用・収益用・遊休不動産など)
- 金融資産(預貯金、有価証券、保険の解約返戻金など)
- その他の資産(会社以外の出資持分、知的財産権、高額動産など)
特に銀行が注目するのは「換金性の高さ」です。すぐ現金化できる預貯金であれば、評価100%とされることが多いです。
それに対して、上場株式だと80%前後、不動産の場合は立地や用途によって30~70%、ゴルフ会員権や高額動産は市場性により評価額が大きく変動します。
また、取得価額よりも実勢価格が大幅に上回っている「含み資産」を持っている場合は、含み益の分も潜在的な返済原資としてプラスに評価される場合があります。
たとえば、取得価額1億円の不動産が現在2億円の価値を持っていれば、その差額の1億円も「有事の際には返済を補う力となる」と認識されるわけです。
3. 実態修正による最終評価
三つ目のポイントは、決算書上の数字を「実態に即して修正」する作業です。
これは企業の財務内容をより正確に把握するために行われ、経営者にとってはプラスにもマイナスにも働く可能性があります。
- 主な修正対象としては、以下のような項目が挙げられます。
- 資産の実態評価(不良売掛金、評価減が必要な在庫、固定資産の実勢価格 など)
- 簿外債務のチェック(リース債務、保証債務、未計上の退職金債務 など)
- 関係会社への影響(関係会社の業績、グループ間取引の実態、債務保証の状況 など)
たとえば、決算書上では債務超過になっている企業でも、土地などに大きな含み益があれば、実態修正後の純資産はプラスになるケースがあります。
こうした事例では、書類上の数字だけにとらわれず、しっかりと三次評価を受けることで最終的な格付けが大きく改善される可能性もあるのです。
三次評価を活用するためのポイント
では、実際に三次評価を上手に活用し、格付けアップや融資条件の好転を狙うためにはどうすればいいのでしょうか。
ここからは、私が実際に見聞きしてきた事例や経験をもとに、具体的なアプローチをいくつかご紹介します。
1. 戦略的な情報開示
まず大切なのは、「包み隠さず何もかも開示しなければならない」という思い込みを捨て、銀行が評価するポイントを理解したうえで戦略的に情報開示を行うことです。
- 効果的な開示のタイミング
- 新規融資の申込時
- 金利の見直し交渉時
- 担保・保証の解除を検討するとき
- 事業承継を考慮し始めた段階
- 開示する情報の選び方
- 換金性の高い資産を中心に
- 含み益のある資産を優先的に
- 返済余力を示せる情報から
開示を行う際には、「なぜこの情報を見せるのか」という目的をはっきりさせ、単に「こんなに資産があります」という羅列に留まらないよう注意しましょう。
銀行に対しては、「自分にはこれだけ返済能力の裏付けがあります」というストーリーを明確に伝えることが重要です。
2. 経営者保証との関係性
三次評価は、経営者保証の解除にも大きく関わります。
近年、「経営者保証に関するガイドライン」の活用が進んでおり、その判断材料として経営者個人の資産力や返済余力が重視されています。
- 保証解除の可能性を高める要素には、以下のようなものがあります。
- 個人資産が会社借入金の20%以上に相当し、しかも換金性が高い
- 安定的な資産運用をしている
- 役員報酬に余裕があり、生活費を差し引いても返済余力が確保できる
- 経営者個人の収入が継続性を持っている
- 実態修正でプラス評価(含み益など)
- 企業としても健全な財務体質と高い透明性を保っている
これらを満たす経営者の場合、銀行に対して「保証を外しても返済能力に問題がない」という説得材料となり、保証解除が実現しやすくなります。
3. よくある失敗パターン
一方で、三次評価を有効に活用できないケースもあります。以下のような対応は、逆効果を生む可能性が高いので避けるべきです。
- 必要以上の情報隠し
- 「すべて担保に取られるかもしれない」という誤解から、まったく情報を出さない
- 不信感を招き、逆にリスクが高いと判断される
- 個人資産の過度な会社活用
- 個人の不動産や預貯金を無計画に担保提供するなど、企業と個人の線引きが曖昧になる
- リスクヘッジがまったくできなくなる
- バランスを欠いた役員報酬
- 企業業績に見合わない急激な増減
- 家族構成や生活実態に即していない報酬設定
こうした失敗パターンを回避するには、銀行が求める評価ポイントをしっかり理解し、企業と個人のバランスを取る視点が欠かせません。
三次評価を味方につけるための具体策
それでは、どのように準備すれば三次評価で高い評価を得られるのでしょうか。実務レベルで取り組みやすいポイントをまとめてみました。
- 現状の棚卸し
はじめに、経営者個人としての資産をリストアップし、正確な評価額と換金性を把握します。また、役員報酬や生活費、家族構成などから、実際にどれだけの返済余力があるかを算出しておくことも重要です。 - 開示戦略の策定
銀行に対してどのタイミングで、どのような情報を開示するかを決めます。たとえば、新規融資の交渉時に不動産の含み益を示すことで、金利を有利にできるかもしれません。あるいは保証解除の場面で、充分な個人資産を提示することで担保の必要性を減らせる場合もあります。 - 資料の準備とストーリー作り
「返済能力の裏付け」として、どの資産をどのように示すかを整理し、数字だけでなく説得力のある説明を作り込むことが大切です。単に保有資産の一覧を並べるのではなく、「この資産は換金性が高く、必要があれば早期に現金化できる」「この不動産は長期的に価値が上昇傾向にある」など、銀行目線での利点を明確にしておきましょう。 - 具体的な活用シーンを想定する
たとえば以下のような場面で、三次評価における情報開示が大きな武器になります。
- 新規融資の交渉材料として
- 金利引き下げの根拠提示として
- 経営者保証の解除を求めるとき
- 事業承継の計画を銀行に示す際
まとめ:三次評価を経営に活かそう
ここまで見てきたように、「三次評価」は決算書の数字だけでは把握できない経営者個人の資産力や返済余力を評価するものであり、融資審査において大きな影響力を持ちます。
特に、個人の資産を「根こそぎ担保に取られる」といった誤解を解消し、銀行が真に知りたいのは「実際に返済を支えられる力がどの程度存在するのか」である点を理解しておくことが重要です。
今回の記事のポイントを振り返ると、以下の3つに集約されます。
- 三次評価の3つの柱
- 役員報酬と返済余力
- 経営者個人の資産内容
- 実態修正による最終評価
- 効果的な活用方法
- 戦略的な情報開示
- 経営者保証との関連付け
- バランスを欠かない対応
- 実務上の留意点
- 必要以上の情報隠しは逆効果
- 個人資産は「返済能力の裏付け」として評価される
- 役員報酬や生活水準との整合性がカギ
私自身の経験から申し上げると、三次評価で好評価を得られている経営者には「個人と企業の健全な線引きができている」という共通点が見られます。
つまり、必要な情報はきちんと開示しつつ、家計と会社の資金管理を適切に分け、無理のない返済計画を立てられる経営者は、銀行からも高い信頼を得やすいのです。
三次評価は決算書の数字だけではわからない部分をカバーできる、大きなチャンスでもあります。
正しく理解して戦略的に情報開示を行うことで、銀行との関係を強化し、結果として企業の成長を後押しする力にもなるはずです。
今後の融資交渉や格付けアップを検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。